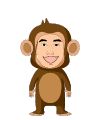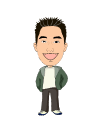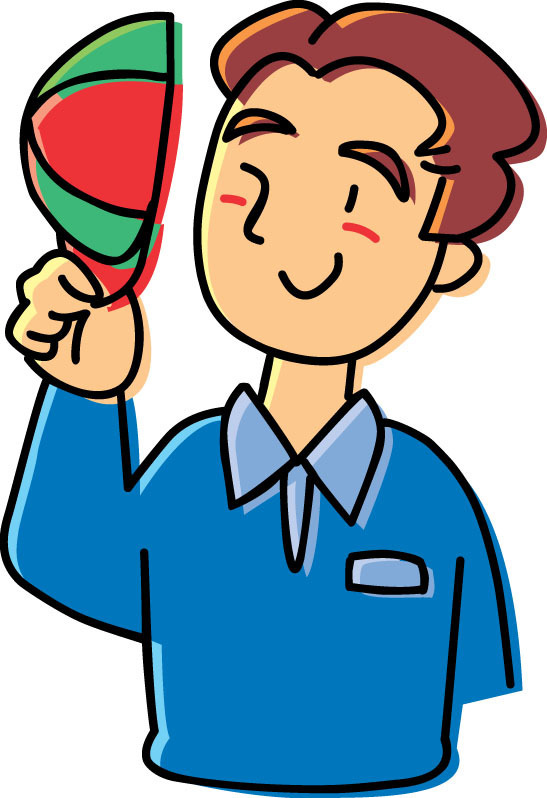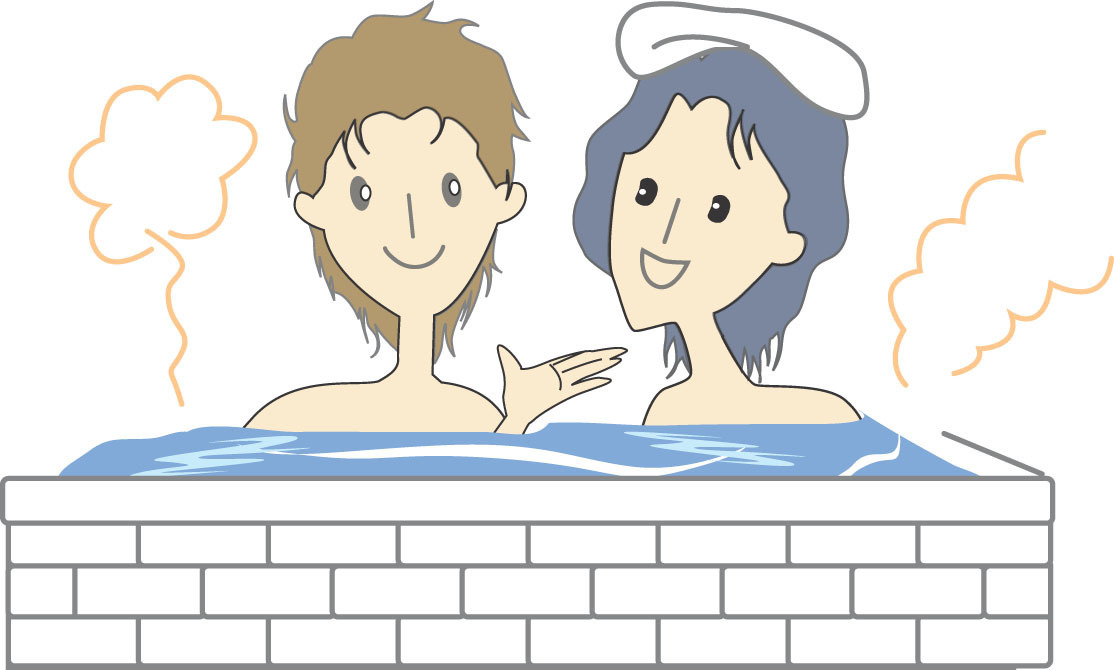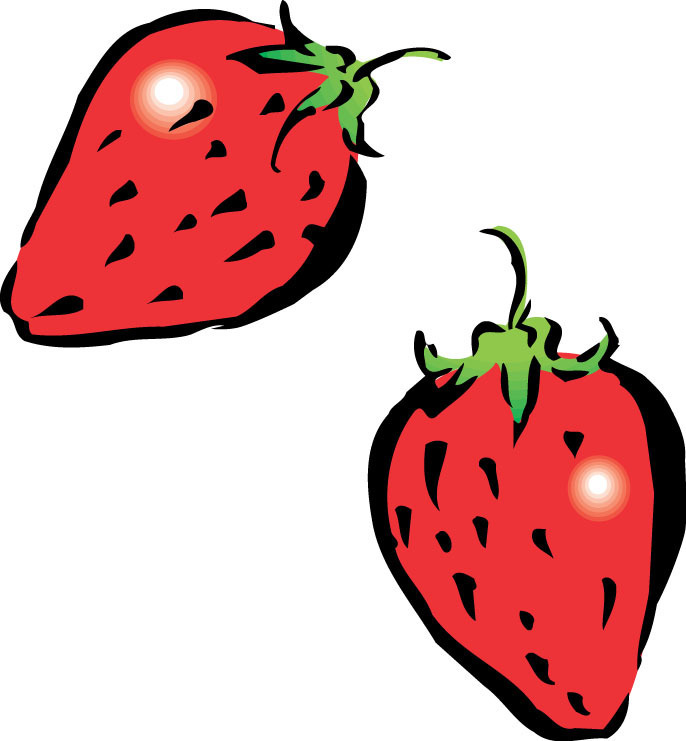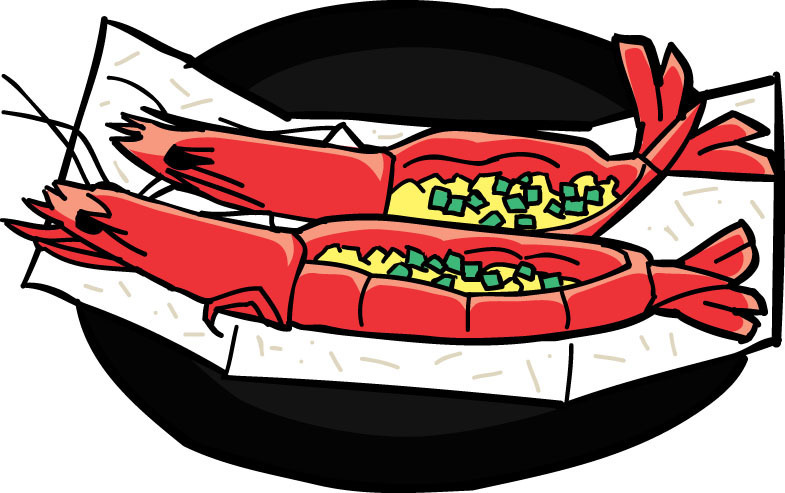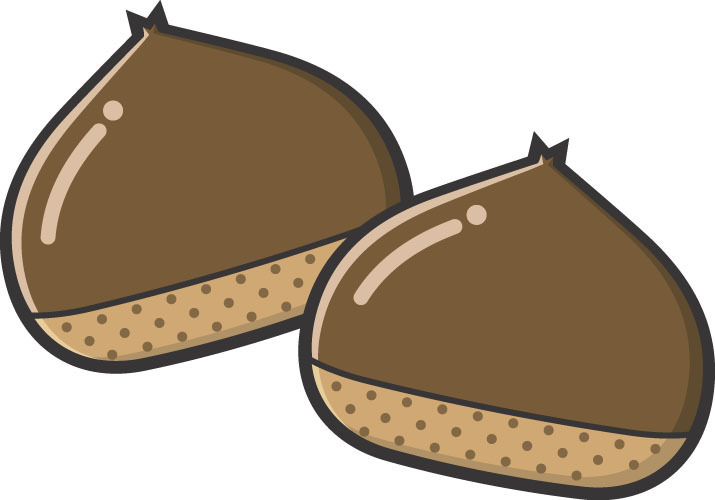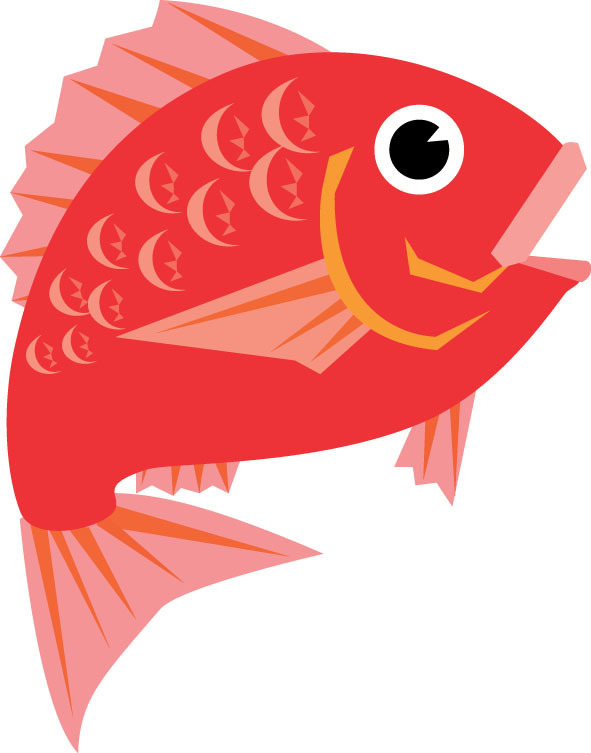幸福カイロプラクティック
(新大宮鍼灸整骨院)
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町2-10-30 高辻マンション101号
近鉄奈良線・新大宮駅徒歩3分
診療時間 | 午前10時~12時 午後 1時~ 8時(土曜日のみ6時まで) |
|---|
休診日 | 日・祝日 |
|---|
変形性頚椎症の治療法について! フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
変形性頚椎症とはどんなものなのか?
まず、ご説明します。何故変形性頚椎症は起こるのでしょう。一般的には老化(加齢)による変化であると言われています。しかし、同年齢の方を比較してみると骨変化の程度は人それぞれで体質・環境・栄養等により違ってきます。
構造的にみると頚椎には頭の重さや上肢の重さが二足歩行と言う人間特有の事情から常に寝ている時以外は掛かってしまいますので徐々に椎間板や椎骨の変形が進んでいくのも仕方の無い部分があるのですが・・・。
次に、どのような症状が出るのかというと、頚椎椎間孔から脊髄神経が出てくる時にストレス(圧迫)を受けた脊髄神経の支配領域にあたる筋肉や皮膚等にしびれ(知覚障害)・筋力低下(運動障害)・痛みが出現することになります。
では変形は大部分老化(加齢)によるものだから仕方が無いものだと、あきらめなければならないのか?と言えばそうでもありません。ご高齢の方でも逆に若い方でも変形性頚椎症で苦しんでおられる方がいるということは老化以外の部分(環境・栄養)が大きいのだと考えています。
カイロプラクティックでは姿勢の歪みがかなり大きな比重を占めていると考えます。それは変形性頚椎症を発症すると言うことは椎間板や椎体部分に充分な新陳代謝(栄養吸収や老廃物の排泄)が行なわれていないことが原因で発症するのではと考えます。
実際、椎間板部分には血管網が存在しません(20歳ぐらいまではある)のでどのように栄養を取り込み、老廃物を排出するのか?大変重要ですね!(椎間板はおおざっぱにいえばスポンジのイメ−ジで考えてもらって、スポンジに上下から圧縮圧を加えたり開放したりすることで栄養や老廃物を代謝している)
いわゆる新陳代謝が何によって行なわれているのかと言えばそれは脊椎の正常な可動性の元に成り立っているものなのです!では脊椎の正常な可動性を保障しているものは何か?
正常な姿勢そのものです!姿勢が歪むとその程度に応じて椎間板の圧縮開放のシステムが充分に働かなくなりますので椎間板の変性(老化)が早まります!次に椎間板を挟む形の椎体変性(老化)が起こり、変形性頚椎症になるのです(重度の変形・変性に陥ると神経の通り道である椎間孔が過度に狭窄を起こしてしまうため手術以外は難しくなる可能性あり)
治療法は簡単!
姿勢調整をすればいいのです。変形した椎間板や椎体による神経のストレス(圧迫)が起こらないように歪みを取り除いてやればいいだけです。言うは簡単ですが出来る治療家は少ないので治療院は選ばなければなりません。間違うと悪化さえすることもありますのでご注意ください。
*ひとつの目安としてポキポキバキバキする治療院は危険です。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
変形性腰椎(脊椎)症の治療法について! フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
変形性腰椎症とはどんなものか?
まず、ご説明します。何故変形性腰椎(脊椎)症は起こるのでしょう。一般的には老化(加齢)による変化であると言われています。しかし、同年齢の方を比較してみると骨変化の程度は人それぞれで体質・環境・栄養等により違ってきます。
構造的にみると腰椎には上半身の重みと歩行や運動動作時の衝撃など大きな力が常に掛かっています。静止時にさえ腰椎(脊椎)にはストレス(圧迫)が掛かっているのです!(人の重心が腰にあるため)
次にどのような症状が出るかと言うと腰椎椎間孔から脊髄神経が出て来る時にストレス(圧迫)を受けた脊髄神経の支配領域にあたる筋肉や皮膚等にしびれ(知覚傷害)・筋力低下(運動傷害)・痛みが出現することになります。
では変形は大部分老化(加齢)によるものだから仕方が無いものだと、あきらめなければならないのか?と言えばそうでもありません。ご高齢の方でも逆に若い方でも変形性腰椎(脊椎)症で苦しんでおられる方がいるという事は老化(加齢)以外の部分(体質・環境・栄養)が大きいのだと考えています。
カイロプラクティックでは姿勢の歪みがかなり大きな比重を占めていると考えます。それは変形性腰椎(脊椎)症を発症するということは椎間板や椎体部分に充分な新陳代謝(栄養吸収や老廃物排泄)が行なわれていない事が原因で発症すると考えます。
実際、椎間板部分には血管網が存在しません(20歳くらいまではある)のでどのように栄養を取り込み、老廃物を排泄するのか?大変重要ですね!(椎間板はおおざっぱにいえばスポンジのイメ−ジで考えてもらってスポンジに上下から圧縮圧を加えたり、開放することで栄養や老廃物を代謝している)
いわゆる新陳代謝が何によって行なわれているのかと言えばそれは脊椎の正常な可動性の元に成り立っているものなのです!では脊椎の正常な可動性を保障しているものは何か?
正常な姿勢そのものです!姿勢が歪むとその程度に応じて椎間板の圧縮開放のシステムが充分に働かなくなりますので椎間板の変性(老化)が早まります!
次に椎間板を上下に挟む形に椎体変性(老化)が起こり変形性腰椎(脊椎)症になるのです(重度の変形・変性に陥ると神経の通り道である椎間孔が過度に狭窄を起こしてしまうため手術以外は難しくなる可能性あり)
治療法は簡単!
姿勢調整をすればいいのです。変形した椎間板や椎体による神経ストレス(圧迫)が起こらないように歪みを取り除いてやればいいだけです。言うは簡単ですが出来る治療家は少ないので治療院は選ばなければなりません。間違うと悪化さえすることもありますのでご注意ください。
*ひとつの目安としてポキポキバキバキする治療院は危険です。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
自律神経失調症・うつ症・パニック傷害・過敏性腸症候群等 0120−155−029(予約優先)
それは交感神経と副交感神経からなる神経系で人間の意志とは無関係に生命維持のために体の調節機能を絶えずコントロ−ルしている。環境に順応できるように自動的に心臓の心拍数を調節したり、呼吸数・体温・発汗量・食欲・睡眠・・・・。とにかく、人間が健康に生きていくため必要不可欠な神経系です。
この神経系が何かの原因でコントロ−ル(調節機能)を失うと大変な事になります。どんな風に大変か?と言えば、今まで普通に出来ていたことが出来ない。急にめまいがしたり、吐き気・耳鳴り・食欲不振・頭痛・不眠・微熱が出たり・身体がだるい・便秘・下痢・血圧変動・・・。
人間が意識して考えることも無く、無意識(勝手)に自律神経系が環境に適応できるように働いてくれていた事ができない状態に陥ってしまった症状のことを自律神経失調症と言うのです。
何が原因で発症するのか?はわかりませんが日常生活のストレス(脳疲労・ホルモンバランスの乱れ・更年期・人間関係・肉体疲労・精神疲労・遺伝的体質・・・)が大きいと言われています。
現代医学的には主に薬剤治療や行動療法が行なわれています。それで問題なく治れば良いのですがうまくいかない場合も・・・。
ではカイロプラクティックはどうでしょう!
カイロプラクティックではどのように治療するのでしょう?考え方としては身体の中に置いて自律神経系がどのように配置されているかが重要です!
自律神経系は頭蓋骨〜脊椎〜骨盤と上から下へ中枢神経系から出る末梢神経系(感覚神経・運動神経・自律神経)のひとつで副交感神経は脳脊髄神経とともに脊柱管の中を走り、交感神経は脊柱の両側を交感神経幹として別に走っている。
つまり、構造的には脊椎骨盤等の歪みは神経系全体に大きな影響をおよぼすのは明白であり、自律神経系もしかり。構造体の不備はそこに属するあらゆる組織に多大な損傷を引き起こすのです!
カイロプラクティックで脊椎骨盤の歪みを正常化することは自律神経系の正常化を導くための有効な治療法と考えています!
治療法としては別にポキポキバキバキと骨を鳴らすような手技は用いませんのでご安心ください。触診等により関節のズレを確認し調整して行くので自分自身の変化を感じてもらいながら進めます。治療ポイントとして頭の付け根・首の付け根・上腰部・骨盤等を細かく調整します。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
変形性膝関節症(半月板損傷・靭帯損傷)等膝疾患について 0120−155−029(予約優先)
現代日本人には膝を痛めて辛い思いをしている方が多くおられます!どれくらい多いか?と言うと日本の総人口約一億二千万人の中で約七百万人もの人が苦しまれているのです!
何故膝は痛くなるのでしょうか?その理由として老化(加齢)変性が挙げられています。さらに肥満・外傷等による関節軟骨の磨耗・変性そして関節そのものの変形へと進むと言われています。
ほんとうにそうなのでしょうか?
たしかに二足歩行する人間の膝には常に大きな力(衝撃力等)が掛かっているので老化(加齢)による傷害は大きく、肥満・外傷等がそれに拍車を掛けて膝疾患を重篤なものにしています。
構造的に膝関節を見ると大腿骨と下腿骨(脛骨・ヒ骨)が上下に合わさって前に膝蓋骨(お皿)が位置します。機能的には屈曲・伸展機能を持っており自由に座ったり、立ったり、正座や胡坐姿勢をとる事ができます。
このように膝関節は屈曲と伸展の機能しか持たないのですが、日常生活に置いては他関節と協調して連動することで多機能性を現します!(ここがポイント)
さて膝関節の治療法はあるのでしょうか?老化(加齢)による変化(変性・変形)だからどうすることもできないのか?痛いのは注射や薬でごまかすしかないのか?病院でのリハビリ(筋力の強化等)はどれほどの効果があるのか?等・・・。
カイロプラクティックではこのように考えます!
たしかに膝関節は日常生活している以上、変性・変形は起こってくるものですが最低限に抑制することは可能だと考えています。つまり、どんな構造物でも使用方法をまちがうと耐用年数が大幅に低下してしまうと言うことです。
膝関節の正しい使用方法とは?
人それぞれ個人差はありますが、二足歩行するためには必ず正しいバランスが不可欠です。各関節間の不適合が存在すれば、そこに無理(力の集中)が生じ、関節変形および周辺軟組織の変性が起こります。
逆に正しく適合していれば何ら無理(力の集中)は生じないのです!カイロプラクティックはその状態に身体を戻すための技術です。何故、膝は変形するのか?それは膝そのものが原因ではなく他関節(足部関節・骨盤・股関節等)にこそ原因があります。
ですから、膝をいくら治療してもほとんど無駄なのです。(敵は本能寺に有り!)治療を受けられればわかりますが、膝治療は身体のバランス調整こそ大事。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
四十肩・五十肩のように肩部に症状を現す疾患について 0120−155−029(予約優先)
肩関節は関節の中で最も可動域が大きく、自由にあらゆる方向に運動することが可能です。しかし、そのため最も傷めやすい関節でもあります。
肩に関する疾患名としては
1、肩関節周囲炎(肩部周辺組織に炎症を発症したもの)
2、肩手症候群(肩部外傷時に交感神経を損傷し発症したもの)
3、肩関節炎(細菌による炎症を発症したもの)
4、肩腱板炎(肩腱板が炎症を発症したもの)
5、肩腱板断裂(肩腱板が断裂したもの)
6、肩変形性関節症(肩関節自体が変形・炎症を発症したもの)
7、上腕二頭筋長頭炎(長頭腱の炎症を発症したもの)
8、肩峰下滑液包炎(肩峰下滑液包が炎症を発症したもの)
9、肩石灰化腱炎(肩腱板部に石灰沈着を発症したもの)
10、肩峰下インピンジメント症候群(腱板が肩峰に衝突または挟まれ発症したもの)
等々たくさんあります。
肩関節に関する疾患をこうして並べてみると理解できると思いますが、炎症を発症したり、細菌感染を起こしたり、石灰が沈着したりというような事が何故起こるのでしょうか?それぞれの疾患名により原因は全く違うものなのでしょうか?
当院の考えている主原因はひとつです(細かくは省く)
炎症や細菌感染や石灰沈着といったことが起こるのは患部の血液循環やリンパ循環が正常ではなく循環不全の状態に陥っているがために炎症物質や石灰分が滞留し、免疫力低下により細菌感染したのではないか?と考えています!
人間をペットボトルに例えると器である容器部分が凹んだり、捻れたりすると中の液体は影響を受けますね。人間の場合、容器が筋骨格で形作られ、容器内の液体が五臓六腑と考えれば容器(筋骨格)が変形すれば液体(五臓六腑)が影響を受けその働きが異常を起こすのは当たり前ですね(逆もあります)
肩関節で考えると肩甲帯(胸鎖関節・肩鎖関節)の変位(ズレ)により上腕骨頭が前方に変位(ズレ)し肩甲上腕関節(肩甲骨と上腕骨との間の関節)・肩峰下関節(烏口突起と肩峰を結ぶ烏口肩峰靭帯と上腕骨との間の関節)・肩甲胸郭関節(肩甲骨と肋骨との間の関節)が変位(ズレ)することで腱板付着部に直接的に狭窄による圧迫ストレスが掛かり、そして腱板筋(棘上筋・棘下筋小円筋・肩甲下筋)の過緊張による牽引ストレスも発生します。
そのため、肩周辺組織の血液循環・リンパ循環が阻害されることで
*炎症物質・老廃物が排泄されず、栄養が吸収されない(炎症性疾患発症する)
*カルシウムの排泄・吸収がうまくいかない(カルシウム沈着が発症する)
*免疫力低下が起こる(細菌感染が発症する)
ことになるのです。
治療法は全体の姿勢調整しながら特に頚胸椎・胸郭部・肩甲帯・上肢の関節不適合を正すことで軟組織(筋・靭帯等)の緊張異常を正常化し血液・リンパ循環を整えます。
*関節不適合(変位)を調整しなければ筋緊張異常は正常化しません。
ほんとうに姿勢調整できる治療家は少ないのでよくよく探してください。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
めまいについて! フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
めまいを発症する病気は多くあります。例えば、
*耳に起因するもの
1、メニエ−ル病
2、良性発作性頭位めまい症
3、内耳炎
4、突発性難聴
5、遅発性内リンパ水腫
6、前庭神経炎
7、聴神経腫瘍
8、その他内耳性めまい
等々、多くあります。
*脳に起因するもの
1、脳血管障害
2、脳腫瘍など・・・。
*全身に起因するもの
1、頚椎疾患からのもの
2、不整脈からのもの
3、血圧異常からのもの
4、自律神経からのもの
5、ホルモン分泌異常からのもの
6、その他・・・。
このように多彩な原因疾患でめまいは発症します。ではカイロプラクティック等の自然治療が有効であるめまいとはどのようなめまい(眩暈)なのでしょうか?
まず言えることは、
1、機能的疾患であること(腫瘍があるとか諸検査で器質的変化が確認されているものは不可)です。
2、はっきりした原因がなくストレス(過労・睡眠不足・食事の不摂生等)によるもの。
3、他の病気から間接的に発症したもの(頚椎疾患・顎関節症・血圧異常等)
4、自律神経失調症によるもの。
などです。
どのような原因であっても内耳や小脳に循環障害が発症した結果めまい(眩暈)が起こっているので治療法としては循環傷害改善を目的として施術することになります(患部だけでなく全身の循環改善)
治療法は姿勢全般の調整の上、特に胸郭周辺部(頚胸椎・胸郭部・肩甲帯)と頭蓋骨・顎関節と筋肉群調整します。
それにより、内耳神経(前庭・蝸牛)・顔面神経や椎骨動静脈(内耳に枝を送る)に掛かる物理的ストレス(圧迫・伸展等)を取り除き正常な機能を取り戻すようにします。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
変形性股関節症について!
変形性股関節症とは、股関節骨頭部が摩滅し変形を起こす病気ですが、臼蓋形成不全のある方や先天性股関節脱臼(発育性股関節形成不全)の既往のある方は、普段から身体の調子には気をつける必要があります。
しかし、なかなか気がつかないで放置してしまう場合が多いのです!
何故か?と言うと股関節症の場合は、当初から股関節部に痛みや異状感を感じることは少なく、膝痛とか腰痛として病院に掛かられる場合がほとんどです。
その理由として、股関節骨頭軟骨に不適切な外力が掛かり、損傷したとしてもその時点では、何の違和感も感じないのです。つまり、神経・血管が無いのでわからないで過ごしてしまい、損傷による炎症が関節を包む関節包内膜の滑膜部分(神経・血管が豊富)に及んで始めて痛みを感じます。
炎症が滑膜部分まで及んでしまい痛みとして認知される頃には、骨頭部に変化を生じている場合が少なくなくX−P(レントゲン)で指摘されるようになります。
ですので、特に股関節に既往症をお持ちの方は、単純に腰痛や膝痛と思い込まず、気をつける必要があります。
対処法として!
変形性股関節症を発症するのは約8割は女性で、股関節部に上記疾患をお持ちの方が大部分ですので当てはまる方はヨガやストレッチ等の自主管理と定期的なカイロプラクティックによる姿勢管理が重要です!
カイロプラクティックによる姿勢管理で重要部分は骨盤の歪みに対する調整になります!
何故か?と言えば、既往症として股関節に疾患をお持ちの方は関節のはまり具合が浅くズレ(関節不適合)易く、正しい位置で体重を受け止めることが出来ず、関節軟骨の摩滅を起こし易いのです!
逆に言えば、正しい位置で体重を受け止めることが出来るように姿勢調整してやれば、予防できる可能性が非常に高いのです(転ばぬ先の杖!)
では、実際どのような治療をするのか?
股関節は骨盤部の寛骨臼と大腿骨頭部からなり、どちらが変位(ズレ)しても関節不適合を生じ、変形を起こし易くなりますので、骨盤の歪みを調整し大腿骨の捻れを同時に調整します(姿勢バランスを診ながら)
それにより、体重を股関節部で正しく受け止めることが出来、関節軟骨の摩滅を最小限に抑えられると考えています。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
坐骨神経痛について
坐骨神経痛は病院でも治療院でもほんとうによく診られる症状ですが原因としては
1、根性坐骨神経痛(腰椎性坐骨神経痛)によるもので約9割がこのタイプ(椎間板ヘルニア等)
2、梨状筋性坐骨神経痛:梨状筋部を坐骨神経が通過する際にストレス(圧迫・伸展)を受け発症するタイプ。
3、症候性坐骨神経痛:直接の坐骨神経圧迫によるものでなく(原因不明)発症するタイプ。
4、脊柱管狭窄症により発症するタイプ。
5、腰椎分離すべり症により発症するタイプ。
に分類できる。
このように分類するとかなり複雑に考えてしまいますが、すべて直接原因は骨盤の歪みによる腰椎捻れにあります。
まず、1、について
このタイプが坐骨神経痛の原因の約9割を占めるのですが、要するに骨盤腰椎の歪み・捻れを調整することで脊髄神経根の出入り口である椎間孔の狭窄および周辺軟組織の過緊張を取り除いてやれば、症状が解消されます。
2、について梨状筋は骨盤の仙骨という骨の前面外側部・大坐骨切痕から起こり股関節の大転子に付着しますので骨盤の歪みに際して仙骨が変位(ズレ)ると梨状筋は過緊張を起こすので坐骨神経にストレス(圧迫・伸展)を与え、結果坐骨神経痛となります。ですから、仙骨の位置を正しく戻してやれば解消します。
4、脊柱管狭窄症に関してはいわゆる脊椎骨の変形が脊柱管の内径を狭窄させるように変形してきたものですから、治療法としては骨盤腰椎の歪み・捻れを調整することで内径の狭窄を減少させることです。よほどの狭窄でない限り症状は改善します。
5、腰椎分離すべり症においても、4、と同じ治療法で改善します(この場合、内径の狭窄はすべり現象で発症しているところが違いです)
では、3、についてですが原因は直接の坐骨神経に対してのストレス(圧迫・伸展)ではなく、間接的にストレス(圧迫・伸展)が加わった結果です。
どういうことか?と言いますと骨盤自体の歪みにより骨盤内臓器群(軟組織)に内圧力が掛かったことで引き起こされた坐骨神経痛だと言えます(慢性化が進行すると発症してきます)
この場合の治療法は通常の1,2、4、5、の治療に加えて内蔵調整・筋膜調整等をします。それで内圧力を整えれば解消します(骨盤内軟組織の癒着等ひどければ難しいことあり)
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
手根管症候群について
手根管症候群で悩まれている方は多いと思います。特に手先の細かい作業や負荷の高い仕事の方に多く発症しているようです。
その発症原因として
1、手関節の使い過ぎによるもの
2、ホルモンバランスの乱れによるもの
3、骨折や脱臼、腫瘤などによるもの
4、リウマチ・糖尿病・甲状腺機能低下等によるもの
5、その他
発症原因は色々ありますが2,3,4,5、のような原因で発症された方は、少ないのではと思っています。1、の手関節の使い過ぎによるものとは、いったいどれほど使いすぎたと言うのでしょうか?
仮に1,2,3,4,5、の原因で発症したとしても二次的に手根管トンネルの内圧力が亢進したが為、正中神経・腱がストレス(圧迫・伸展)を受け症状としてしびれ・痛み・拇指球の萎縮が出現しているのです。
ですから、原因は1〜5のどれであっても治療法としては手根管トンネルの内圧力を正常まで低下させてやることです。
手根管トンネルは屈筋支帯と手根溝(大・小菱形骨・有頭骨・有鉤骨)で構成されたもので、その中を正中神経・とう側手根屈筋腱・長母指屈筋腱・浅指屈筋腱・深指屈筋腱が通りますから内圧力亢進の影響を受けます。
治療法としては手根管トンネルの内圧力を正常まで低下させなければなりません。ではどうするか?と言えば内圧力が亢進した原因を治せば良いということです!
内圧力亢進の原因は手根管トンネルの形成不全(歪み)だと考えていますので手根溝(大・小菱形・有頭骨・有鉤骨)を形成する4個の骨の関節不適合(ズレ)を整えることで内圧力を正常に戻すことが可能だと経験的に実証しています。
手根管トンネルが歪めば中を通る神経や腱はその影響でストレス(圧迫・伸展)を受け症状を発症することは容易に理解できるものと思います。
*実際の治療時は姿勢全般の調整の上施術いたします!
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
顎関節症について!
顎関節症でお悩みの方は多いと思います!軽症から重症まで色々おられますがほんとうに辛いものです顎関節症の症状として
1、顎が痛む。
2、口が開けられない又は閉じれない。
3、顎が鳴る。
4、噛み合わせに違和感がある。
等が多いのですが、要するに顎関節の運動障害です。
何故、このような症状が起こるのでしょうか?
原因には不良歯列によるものや、噛み癖によるもの、普段の習慣的不良姿勢(ほお杖・猫背・寝方等)、顎関節の打撲・口の開けすぎ等考えられます。
どちらにしても、顎関節周辺組織の変性・変形が進行しているものほど治療は難しくなります。しかし、カイロプラクティックにて姿勢調整することで改善さすことは可能であり重症化を予防できます。
カイロプラクティックにより顎関節症が改善する理由として筋骨格系の改善・正常化が挙げられます。
まず、下顎骨に付着する筋群を考えると
1、側頭筋
2、咬筋
3、翼突筋(内側・外側)
4、顎二腹筋(前腹)
5、顎舌骨筋
6、オトガイ舌骨筋
等があり、その他下顎骨を動かす筋群はたくさんありますし、そのどれもが正しく機能しなくては顎関節運動機能は成立しません(顎関節症を発症してしまうことになる)
顎関節は上下・左右・前後の運動が可能ですので、すべての筋群が協調して動かなくては左右顎関節の変位(ズレ)が生じてしまいます。
例えば、側頭骨の変位(ズレ)が起これば側頭骨部にある下顎窩も変位(ズレ)するので顎関節の不適合が起こります。そして側頭筋も筋緊張異常を起こしますので左右顎関節のシンクロ(同期運動)が崩れ異常運動が発症します。
例えば、胸骨舌骨筋・胸骨甲状筋は胸骨と舌骨・胸骨と甲状軟骨の間に張る筋肉で舌骨を通じて下顎骨に付着します。もし、胸郭上部の歪みがあれば胸骨も変位(ズレ)し、上記筋群の緊張異常を発症します。すると、舌骨を通じて下顎骨を引っ張るベクトル(方向)が変化するので顎関節に無理が生じます。
例えば、肩甲舌骨筋は肩甲骨上縁と舌骨に張る筋ですが肩甲帯(肩甲骨・鎖骨)の変位(ズレ)により筋緊張異常を起こし、舌骨を通じて下顎骨を引っ張るベクトル(方向)が変化するので顎関節に無理を生じさせます。
このように、顎関節症とは顎関節だけの問題で発症するのではなく、姿勢バランスの崩れにより発症するのだと考えるのが正しいと思います。
カイロプラクティックで顎関節症が改善する可能性が高いと言うことが、理解してもらえれば幸いです!
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
腰椎分離症(辷り分離症)について!
成長期の子供たちに多く見られると言う腰椎分離症(椎弓部の疲労骨折)ですが、スポ−ツ等で身体に過度の外力が掛かったり、肉体疲労の蓄積により柔軟性を失った筋骨格に無理な外力が働き、発症してしまうことが多いようです。
一度、腰椎分離症を発症してしまうと元に戻すことは難しく以後の運動には身体の管理・調整が欠かせません!
症状的には運動時腰痛や背部痛ですが再発しやすくスポ−ツ等に限らず、身体を酷使するようなことは気をつけねばなりません。特に身体を強く捻るとか傾けるような動作により、特定の腰椎椎弓部に過度の牽引力が掛かり発症する場合が多いので要注意です。
治療法はカイロプラクティックで姿勢調整をすることで(骨盤調整が重要)特定の腰椎椎弓部に過度の牽引力が働かないように分散させることができます。
理由として脊椎・骨盤の関節は約25〜30個あり、二足歩行を行なう人間はバランスを取りながら動く為に全ての関節を過不足なく動かしているのですが、もし骨盤・腰椎の動きに偏りが発生すれば骨盤・腰椎に付着する筋群(実際は全身に及ぶ)に過剰な負担や牽引力が生じるのは当然ですね。
その結果、腰椎分離症を引き起こすのですが、発症後の管理としても起こした原因である姿勢バランスの調整治療は有効なのです!
*ほんとうに姿勢調整できる治療家は少ないのでよくよく探してください。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
後縦靭帯骨化症・黄色靭帯骨化症について!
身体が硬くて、柔軟性が悪いだけだと思っていたら、いつのまにか手足が痺れてきたり細かな手先の動作がし難くなってしまった。X−PやMRIで検査したら後縦靭帯硬化症・黄色靭帯硬化症だった。
つまり、脊柱管内径が後縦靭帯肥厚や黄色靭帯肥厚により狭められたことで中を通る脊髄を圧迫し機能低下を起こした結果、上記症状が発症してきたのです。
脊髄への圧迫がひどくなるにつれ、日常生活の支障(鉛筆が持ちにくい・箸がうまく使えない・歩きにくい・階段の昇り降りがうまくできない)とか手足のしびれ等、神経機能低下による各種症状が発現します。
何故、このようなことが起こるのか原因は不明ですが、ある程度の予防と症状悪化を遅らせることは可能です!
靭帯が肥厚する原因の一つとして考えられるものに姿勢バランスの悪さがあります。脊椎・骨盤はたくさんの関節(約25〜30個)で構成されています。
そのことにより、二足歩行等の人間行動を行なうときに発生する外力を、各々関節部にて分散消去させることで何の構造的問題も起こさずに生きていけるように創られています!
もし、その関節が姿勢バランスの悪さにより歪み・捻れたりして固定化を生じてしまうと、その部分に外力が集中し、炎症を起こし靭帯部分では肥厚という変化が起きてしまいます。そして、カルシウムが沈着するようになり骨化してしまうのです。
手術と言う選択肢は最終手段として考えなければなりませんが、大きなリスクを伴うものだけに保存的治療を優先する必要があります。
保存的治療法の一つとしてカイロプラクティックがあり(ポキポキ・バキバキは不可)、姿勢バランスの改善を行なうことで症状緩和できると考えています。もちろん、患部に負荷を掛けるような治療は致しません。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
頚椎症性脊髄症について!
人は加齢することで肉体が衰えることから逃れることはできません!
頚椎を形成する組織が徐々に加齢変化を起こし、椎間板狭窄・椎体骨棘・靭帯肥厚等が生じ、脊柱管内径が狭められ、中を通る脊髄圧迫を発症したことで日常生活全般に支障を来たしてしまう病気です。
手足が痺れたり、歩行・階段の昇り降り・服のボタンがとめ難い・字が書けない・箸が持てない等々の症状が発現してきます。
進行してしまうと手術以外方法はありませんが、そこまで重症化する前に保存療法で予防・進行を遅らせることは可能です。
同じ年齢でも頚椎の加齢変化には大きな個人差があり、上記した椎間板狭窄・椎体骨棘・靭帯肥厚がほとんどなく健康に過ごしておられる方は大勢います。
このような差はどうして起こるのでしょうか?
そのひとつの答えとして、姿勢バランスの良し悪しがあります。姿勢バランスが悪いと椎骨が捻れ、固定化を起こすことで椎間板の充分な代謝(栄養・排泄)活動が阻害され、老化現象である狭窄という変化が起きます。そして椎体・靭帯部分には過度な外力が掛かることで炎症が生じ、骨棘・肥厚という変化が生じるのです。
ですから、普段からカイロプラクティックにより姿勢バランスを整えることで予防できる可能性があるだけでなく、不幸にして上記症状を発症している方であっても症状緩和や進行を遅らせることは可能です。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
腰椎椎間板ヘルニアについて!
人類の約半数は何らかの腰痛を経験すると言われています!その中で腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛も大変多い原因となっています。
症状としては、腰痛・臀部痛に加えて下肢のしびれや突っ張り・筋力低下等ですが、ひどくなると手術適応となる場合もあります。
何故、椎間板ヘルニアを発症するのか?と言えば、偏った姿勢であるとか、腰に負担の掛かる動作や作業等が考えられます。
詳しく説明すると、姿勢バランスが正常であるのなら理論的には椎間板ヘルニアは発症しません!何故なら腰に掛かる負担が適切に分散していれば一箇所に集中して外力が掛かることが無いからです。
つまり、人間の骨格構造上、骨盤の歪みが起こると脊柱(腰椎)の捻れが生じ、腰椎がロック(固定化)を起こし椎間板に偏った外力が掛かります。そして椎間板変性〜椎間板ヘルニアと変化して行き症状を発症してしまいます。
ですから、予防法としても治療法としても姿勢バランスを整えることが重要であり必要なのです!
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
オスグッド病について!
10歳〜15歳くらいの成長期の子供に多く見られるもので成長痛とも呼ばれる症状です!
膝関節の過度の曲げ伸ばしを繰り返すようなスポ−ツで起こりがちだと言われていて、大腿四頭筋が膝蓋骨を介して脛骨結節(すねの上端部)を過度に牽引することで骨端線が剥離し生じる症状です。
何故、筋肉による過度の牽引が掛かってしまうのでしょうか?全てのスポ−ツをする子供が罹患するのでしょうか?同じ運動量を行なっても罹患しない子供との違いは何なのでしょう?
それは、姿勢バランスの違いなのです!骨盤や下肢関節に歪みや捻れがあると関節部だけでなく、筋肉(この場合は大腿四頭筋)にも過剰な緊張が起こるため、成長痛なる症状が発生するのです。
カイロプラクティックで姿勢バランスを改善すると、早期に剥離し炎症を持った脛骨結節部の改善が見られます(スポ−ツへの復帰が早まります)
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
胸郭出口(斜角筋・肋鎖・小胸筋)症候群について!
腕を上げたりする動作(棚の上の物を取る・鉄棒にぶら下がる・洗濯物を干す・電車のつり革を持つ等)をすると、手や腕肩が痺れたり痛んだりするような症状を生じる時、胸郭出口症候群が疑われます!
ひどくなると、手指の巧緻動作(字がうまく書けない・箸が持てない等)・筋力低下・手内筋の萎縮等も生じることもあります。
何故、このようなことが起きるのか?と言えば、骨格構造の歪みにより引き起こされたもので神経や血管への物理的ストレス(圧迫・伸展)が原因です。
胸郭出口周辺には3箇所ほど構造的に神経・血管に物理的ストレス(圧迫・伸展)を与える可能性のある箇所が存在します。
1.前斜角筋と中斜角筋の間を神経・血管が通過する部分(斜角筋症候群)
2、鎖骨と第1肋骨の間を神経・血管が通過する部分(肋鎖症候群)
3、肩甲骨烏口突起部に小胸筋が付着している内側を神経・血管が通過する部分(小胸筋症候群)
以上ですが、いずれも重症例では手術にて筋切除や骨切除にて神経・血管のストレス(圧迫・伸展)を解消しようとします。はたして、そのような治療法は正しいのでしょうか?
私は間違っていると思います!
何故なら、患者さんは誰も生まれたときから胸郭出口症候群に罹患してはいないからです。何らかの原因で発症したに過ぎないのですから・・・。
では、治療法はどうするのか?
1、については前斜角筋は第3頚椎横突起〜第6頚椎横突起から起こり第1肋骨に付着する。中斜角筋は第2頚椎横突起〜第7頚椎横突起から起こり第1肋骨に付着する。前・中斜角筋の間の間隙を腕神経叢が通過するのですが、頚椎の捻れや第1肋骨の歪みが生じると前・中斜角筋の過緊張が起こり、神経・血管を挟み込む状態になり症状が発現します。
2、鎖骨と第1肋骨の間の間隙を神経・血管は通過するのですが、鎖骨と第1肋骨が歪むと神経・血管を挟み込む状態になり症状が発現します。
3、小胸筋付着部の内側を神経・血管は通過するのですが、小胸筋は第3肋骨~第5肋骨から起こり肩甲骨烏口突起に付着しているので、肩甲骨や肋骨の変位(ズレ)が生じると小胸筋付着部内側部分が狭窄状態になるので神経・血管にストレス(圧迫・伸展)が掛かり、症状が発現します。
以上、1,2,3、のどの場合でも、姿勢バランスの崩れから胸郭出口周辺組織のバランスが崩れ、症状発現に繋がっています。
治療法はカイロプラクティックにて姿勢バランスを改善すれば解消します!
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
肘部管症候群について!
肘部管症候群とは、肘内側部を通る尺骨神経が何らかの原因で慢性的にストレス(圧迫・伸展)を受け、発症する症状(しびれ・麻痺・変形・萎縮等)です!
主な原因に
1、関節部周辺にできるガングリオンによる尺骨神経へのストレス(圧迫・伸展)
2、加齢変形による尺骨神経へのストレス(圧迫・伸展)
3、肘関節骨折に伴う変形による尺骨神経へのストレス(圧迫・伸展)
4、スポ−ツ等で無理が掛かり、尺骨神経にストレス(圧迫・伸展)が生じた。
5その他
ですが、病院での治療法としては薬物療法や安静と言った保存療法が初期治療法として行なわれ、重症化すれば手術療法が行なわれます。
肘部管症候群とは要するに何らかの外力(ガングリオン・骨折変形等の物理的神経刺激)で尺骨神経がストレスを受けた結果、上記症状を呈するものですから薬物療法や安静と言ったことでは根本的治療法にはなりません。しかし、早急に手術療法を選択するのもどうか?と思います。
原因3,5以外の1,2,4、に関してはカイロプラクティックが最初に行なう治療法として最善の治療法と考えています。何故なら1、のガングリオンは関節の変位(ズレ)により生じるものであり、2、の加齢変形しかり、4、のスポ−ツ等の無理が掛かった状態しかり、すべて関節変位(ズレ)によるものなのです。
3、は骨折時の整復不全による影響が大きいのでケ−スバイケ−スですが、悪化しない内にカイロプラクティックを試されるのが良いと思います。
肘関節は腕橈関節・腕尺関節・上橈尺関節の3つの関節から成り、複雑な動きを可能にしています。尺骨神経は上腕骨の内側上顆後面の尺骨神経溝を通過していますので、腕尺関節の変位(ズレ)は尺骨神経に特に大きなストレス(圧迫・伸展)を与えます。
肘関節が変位(ズレ)を起こすことで、関節を形成する組織群(関節軟骨・関節包・靭帯・等)に変形・変性等の変化が生じて肘部管症候群が発生しますので、関節変位(ズレ)を調整することが重要です。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
アキレス腱炎について!
アキレス腱はどこにあるか?と言えば、ふくらはぎ(下腿三頭筋)が踵骨に付着する約15センチぐらいの太い腱の部分です。
この腱部分には血管分布が少なく一度,傷めたりして炎症が生じると治り難い部位です。運動不足にも関わらず急激な負荷を掛けたりすることで、アキレス腱断裂やアキレス腱炎を引き起こすことが多く予防するには運動前のストレッチ等を心掛けなくてはいけません。
しかし、充分にストレッチ等万全の予防策を講じていても傷めてしまう事があります。何故でしょうか?
それは、姿勢バランスの崩れが原因と思われます。姿勢バランスが崩れていると身体に掛かる負荷の偏りが生じるのでアキレス腱に過負荷が生じれば断裂・炎症等が発生します。
分かりやすく説明しますと、下腿三頭筋の内、腓腹筋は大腿骨(内側・外側)上顆から起こり、ひらめ筋は脛骨・腓骨の上端部から起こり、合わさってアキレス腱として踵骨に付着します。
もし、膝関節部に変位(ズレ)があったり、踵骨に変位(ズレ)があればその間に張っている下腿三頭筋に過緊張が生じます。また、神経支配から考えると、腰椎骨盤の歪み捻れがあると坐骨神経を通じ脛骨神経に影響が出て、下腿三頭筋の過緊張が生じます。
ゆえに、過緊張状態にある筋肉に急激な負荷が掛かると筋傷害を発生し易くなるのです!
治療法はカイロプラクティックで姿勢バランスを調整すれば解消します(断裂している場合は病院での治療になりますが、炎症状態であれば治療できます。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
肋間神経痛について!
肋間神経痛も大変辛い症状で,苦しんでおられる方も多いと思います。
何故、肋間神経痛が起こるのか?と言うと呼吸する時、胸郭を形成する(脊柱・肋骨・胸骨)が上下前後左右に拡がるように動くのですが、脊柱(椎骨)と肋骨は肋骨頭関節と肋横突関節で関節していて胸郭運動(呼吸)時の支点となります。
自分の身体で考えてもらうとわかり易いと思いますが、脊柱(背骨)は後ろにあり、肋骨は前方に向かって円を描くように拡がっています。
脊柱(背骨)を支点にして呼吸運動は行なわれるので、もし胸郭に歪みがあれば支点である肋骨頭関節・肋横突関節に変位(ズレ)が生じ、胸郭運動に影響が現れます。
つまり、固有背筋群(回旋筋・多裂筋・棘筋・棘間筋等)や肋骨筋群等の筋緊張異常(過緊張)により、胸神経がストレス(圧迫・伸展)を受けることで枝である肋間神経に影響が生じ、肋間神経痛が発症するのです。
治療法はカイロプラクティックで肋骨頭関節・肋横突関節の変位(ズレ)を骨格調整すれば、筋緊張異常が正常化し神経ストレス(圧迫・伸展)が取り除かれ解消します。
フリ―ダイヤル:0120−155−029(予約優先)
お問合せ・ご相談
診療時間:午前10時~12時
午後1時~8時(土曜日のみ6時まで)
休診日:日・祝日
近鉄奈良線・新大宮駅徒歩3分!カイロプラクティックや鍼灸整骨院をお探しなら、幸福プラクティック(新大宮鍼灸整骨院)にお任せください。腰痛・肩こり・膝痛・頭痛をはじめ、うつ・ヘルニアなどのご相談も承っております。当院はカイロプラクティックを根幹に鍼灸治療も可能です。奈良県奈良市を中心に、生駒市・木津川市で治療院をお探しの方のご来院もお待ちしております。
お問い合せ

お電話でのお問合せ
お問合せはお気軽にどうぞ
<診療時間>
午前10時~12時
午後 1時~ 8時(土曜日のみ6時まで)
※日・祝日は除く
幸福カイロプラクティック
住所
〒630-8114
奈良県奈良市芝辻町2-10-30
高辻マンション101号
アクセス
近鉄奈良線・新大宮駅徒歩3分
診療時間
午前10時~12時
午後 1時~ 8時
(土曜日のみ6時まで)
休診日
日・祝日